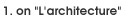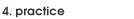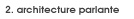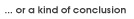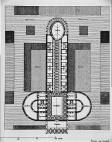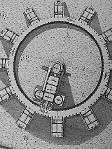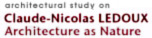自然としての建築
自然は人間本性としてひとびとのうちにア・プリオリに刻み込まれており、その声に従う限り人間は誤謬に陥ることはない。しかし今や、そのような自然状態は失われ、ひとびとの習俗は矯正される必要がある。18世紀のフィロゾフたちはそう考え、そしてその手段を法や教育に求めたのだった。
ルドゥーにとっても、その同時代観に変わるところはなかった。だが、彼の手には建築という至上の芸術がある。それは「もうひとつの自然」であり、自然同様つねに善なる方向へとひとびとを導いていくものである。そしてそのことは、建築物がその外観をとおしてひとびとに「語りかける」ことによってなされるとルドゥーは信じた。これがいわゆる「語る建築 architecture parlante 」★9である。
カラクテールとは古典主義建築理論を代表する術語である。その使われ方は論者によって様々だが、一般化すれば、建築物は配置、平面、立面、装飾、材料等、あらゆるレベルにわたって、その用途 destination と社会序列 rang に適ったものでなければならないとする、いわばシニフィエを建築の社会性に求めた一種の類型学的な表象理論であった。だが、18世紀末期になると、その意味するところは若干変わってくる。ル・カミュ・ド・メジエールやブレは、そこに感覚的な要素を付加するのである。彼らのカラクテ−ル理論は、建築物はその全体、マッスの対比、プロポーションによってひとびとの感情に直接訴えかけることができるとする建築感覚論ともよべるものであった。たとえばル・カミュは『建築精髄---この芸術とわれわれの感覚とのアナロジー Le gènie de l'architecture, ou l'Analogie de cet art avec nos sensations 』(1780)と題された著書の中で、建築を「語るもの」として考察したのは彼がはじめてだとしながら、次のようにいう。
ここにおいて、カラクテールという語が指し示すものは、建築の社会性(建築物の社会における用途、建築主の社会的地位)から、その外観の特徴やそれがひとびとに与える感覚的な効果へと移行を見せはじめている。とはいえ、ル・カミュにあっては依然としてシニフィエとしての社会性は保持されたままであり、その移行が深められるのはブレを待たなければならない。
ブレのカラクテール論は、ル・カミュ以上に建築物がわれわれの感覚に与える効果に力点が置かれ、上のようにそれは明確に定義されている。類型学的・分類学的な意味を持つものから、感覚的・感性的な効果を中心とするいわば情念論的なものとしてカラクテールは捉え直されているのである。だが、ブレにあっても、社会序列はもはや述べられることがないとはいえ、その「主題」を建築物の用途に求めたことにかわりはなかった。
このように元来、建築物の社会序列と用途に基礎を置いていたカラクテ−ル論は、18世紀も末になると、建築物の用途とそれがひとびとに与える感情的効果を統御するものへと、その意味するところが変わっていったのである。★14
この後者のカラクテールを表象のレトリックとして---またしても---極端に押し進めたものがルドゥーの「語る建築」である。彼はこのふたつ(建築物が持つ社会的機能の表象と感情)が一体となることによってひとびとを導いていくことができるという確信、すなわち感情・感覚をとおして経験される建築物の道徳的・教訓的力に対する確信を強固なまでに有していたのだが、なぜそれが可能なのかはどこにおいても考察されていない。ただ、そのような確信に基づいた言葉とドローイングが残されているだけである。ここでは、それを追っていくだけに留めておこう。
「語る」ためには、言語がなければならない。
ルドゥーはそれを幾何学的形態として選んだ。
なぜ幾何学なのか。それは次の言葉が明らかにしてくれるだろう。
ここで話題とされているのは理想都市ショーのための田園住宅であるが、そこではカウフマンがいうところの「革命様式」が遺憾なく展開されている。まったく滑らかな壁面、まぐささえ省略され単に壁が切り取られただけの開口部、正方形によって構成された平面と断面、屋階に突如として挿入されたシリンダーなど、この住宅はルドゥー晩年の手法を余すところなく伝えており、装飾は一切排除されている。なぜなら装飾は「表現的な性格(L.12)」をしており★15多くを語りはするが、ともすれば単なる饒舌に堕すだけだから。
またそれは、「何も見えないひとびと」、すなわち教養のない労働者たちには---彼らこそが誰よりも啓蒙されるべきなのに---ひとことも語りかけることがないからである。
ルドゥーにとって、芸術は万人の間に差別なく等しくあるべきものだった。したがって、見る者を選ぶ《装飾》は当然廃棄されなければならない。そして、それに代わるもの、すべてのひとびとに遍く読解可能であり読みやすい言語とは、最も簡素なそれ、すなわち幾何学的形態だったのだ。
だが、そうして選ばれた幾何学的形態も単に恣意的に組み合わせただけでは「語る」ことはできない。語が意味をなす文となるには統辞法となる体系が必要である。
ルドゥーは、この体系の主題を同時代の他の建築家たちと同様、建築物の用途に求めた(社会序列は問題とはならない。ルドゥー的世界においては基本的に万人は平等であるのだから)。すなわち、幾何学的形態は、建築物の機能を表象するべく組み合わせなければならないのだ。たとえば、オイケマ Oikema ★16と名付けられた閨房の平面図は男性器を露骨に表し、樽の箍 Cercles 職人の工房は円形 cercles そのもののファサードを持つ(また、この工房はショーの外れの四ツ辻に位置し、都市に出入りする者を監視する機能も合わせ持つ。つまり、円形のファサードは同時に目の表象でもある)。それらの表現は実に直截的で曖昧なところが一切ない。なぜなら、それこそが建築のカラクテールであり、あるゆるひとびとに容易に読み取られるものでなければならないからだ。
こうしてルドゥーは、建築の表象の根拠を幾何学と機能に置くにいたった。教会や宮廷だけではなく、一般市民の住宅や工場さらには閨房までもが、ルドゥーにとっては《高貴なる建築 high architecture》でなければならなかったわけだが、そのとき、建築を支えるものは当然ながらもはや《神》や《王》の言葉ではありえない。それは、《社会》の言葉に取ってかわられる必要があったのだ。
ローマ期以降、建築は神の威光や王の権威を表象することをその使命としていた---逆にいえば、それらは自明のものとして意識することなく建築の根拠を背後から支えてくれる頼もしい存在でもあった---のだが、18世紀になると神や王が否定されることにより、建築の表象システムは根拠を失い激しく揺らぎはじめるようになる。その根拠をそれらとは別のところに求めた結果、あるものはそれをローマやギリシヤを超えた(架空の)始源に見い出し、またあるものは建築が持つ社会性のうちに据えようとした。そうして得られたものが幾何学的形態でありカラクテールという表象理論でありあるいはプロト機能主義とよばれる素朴な計画論だったのだが、いずれにせよこれらの試みは建築の《外部》にではなく、その《本性 nature》に建築の根拠を見い出そうとするものであったといえるだろう。だが、ルドゥーは、それにとどまらず、建築の根拠を世界それ自体の根拠である《自然 nature》のうちに求めたのだった。したがって、彼の建築がそれらの試みをすべて呑み込み、よりラディカルに押し進めたものであったとしても何ら不思議ではない。18世紀に「建築=自然」と唱えた時点で、そのような在り方/行き方は運命づけれらていたともいえるだろう。そしてなにより、そのような過剰さこそが《自然としての建築》に相応しいといえはしないだろうか。