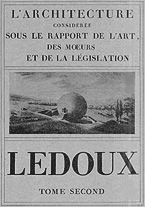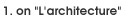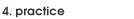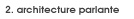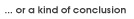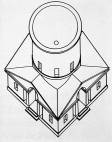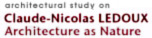『芸術・習俗・法制との関係から考察された建築』
作品集を自ら纏め刊行しようとするルドゥーの計画は1777年にまで遡る。 当初のそれは、実作/計画案を問わず彼の手によるすべての建築物を寄せ集めた単なる銅版画集として考案されており、現在わたしたちが手にすることのできるもののようにはテクストを伴っていなかった。王室付きの建築家として世俗的な栄華の絶頂にあった当時の彼は、その作品集を、何よりも自らの権威を象徴するものとして企図していたのだろう。じじつ、革命の勃興を眼前に控えた1789年の春、単に『C・N・ルドゥーの建築』と題されたそれは、273葉のドローイング・コレクションとして、ロシア皇帝であるパウル一世に献上されている。だが、彼の栄華の極みを巷間に印象づけたこの挿話はまた、その最後を飾るものでもあった。
革命による王室の崩壊。それに伴い、王の建築家であったルドゥーの立場も一転する。投獄、そして斬首台へ。彼自身が伝えるところによれば、まさにロープが断ち切られようとするその瞬間、死すべき受刑者は実は同姓同名の別人であったと判明したため、かろうじて死から免れえたとのことである。だが、そうして生命こそとりとめたものの、その後は《沈黙》を余儀なくされることになる。入市税取立所としての機能を持つパリの市門群、生産=労働=管理のシステムが都市的スケールで展開された王立製塩所ショー。王の命のもと、これらの国家的プロジェクトをものした建築家に、もはや「市民」のための仕事が任されることはあろうはずもなかった。出獄を許された後も、仕事のない建築家の常として、自室に籠り、決して実現することのないだろう計画案やあてどもない想念を描き書きつけながら、ただ日々を過ごすのみであったろう。しかし、この10年余りに及ぶ《沈黙》---ルドゥー自身は「12年間の眠り」(P.xi)と些かヒロイックな表現をこれに与えている---こそが、百数十年後に彼の名を知らしめ、現代においてもなおプロブレマティークであり続ける『建築書』を生み出すことになるのだ。
1804年、その初版が刊行される。ルドゥーは当初、全5巻として『建築書』を構想しており、これはその第一巻に当たるものだった。だが、2年後の脳卒中による突然の死のため、2巻目以降は日の目を見ることなく、結局、彼自身によって出版されたのはこの第一巻のみである。現在の『建築書』は2分冊だが、これは、1847年にいちはやくルドゥーを《発見》したダニエル・ラメが残りの4巻のために用意されていた図版を第一巻と合わせ編集しなおしたものを原型とする。このラメ版以降、幾つかの図版の省略/再掲が行われた以外は、図版やテクストの順序が入れ替えられることはあっても、その内容自体は初版から変わることはない。
だが、そこではすでにルドゥー自身による《編集》が行われていた。『建築書』には、ルドゥーの代表作としてよく取り上げられる《幻視的》な計画案だけでなく、革命以前、彼が王の寵妃であるデュバリー夫人をパトロンとしていた頃に設計し実際に建てられもした幾つかの貴族邸宅の図版が収められているのだが、それらは実作をそのまま図面にしたものではなかったのだ。古典主義の趣が色濃く残る実作は、図版にあっては、彼の理想都市を構成するものとして《沈黙》のあいだに描かれた住宅群に見られる、幾何学的形態を強調したカウフマンいうところの「革命様式 the revolutionary patterns」★1により近いものへと改変されている。また、それだけではなく、作品の配列は年代順に従うとその序文に記しながらも、これもルドゥー自身によって改編されていることが今では明らかとされている★2。『建築書』に収められた建物の多くは文字どおりの理想都市・半=非在郷ショー Chaux のために新たに描かれたものだが、そればかりでなく、彼は、自己の過去までをも書き換えることによって、ひとつの理想世界をこの書物の中に築こうとしていたのである。《書物としてのユートピア》あるいは《ユートピアとしての書物》。
では、ルドゥーは、この《ユートピア》にどのような意図を託していたのだろうか。何が、彼をして文字どおり私財を投げ打ってまでの、この著作の出版へと駆り立てたのだろうか。彼は『建築書』の序文を以下のようにはじめている。
しかし、その記録をまとめ、そこに芸術がもたらした範例と原理を集成すれば、芸術それ自体に傑作を生み出すことを可能にする創造的衝動を起こさしめ、芸術の領土と栄光を拡大することができると信じ、私はここにわれわれの時代の富みをすべて集めたのだ。(L.1)★3
傲岸なまでの自尊心。だが、そうした態度を裏打ちするのは、時代の寵児あるいは王の建築家としての気取りなどではもはやなく---すくなくとも彼の言葉に従う限りは---自己の才を確信し芸術の救世主として深い淵から立ち上がらんとするパセティックなまでの意志である。そして、それとともに、この書『建築書』も、単なる作品集から次のような意義を持つものとして捉え直されている。
同時代の建築家たちには、いわば範例集として、そしてまた、
後生のものには、建築の「永遠不変の規範」(L.9)を指し示す教科書として、いくぶん尊大すぎると思えるほどの啓蒙的な役割を、『建築書』はルドゥー自身によって担わされているのである。
だが、残念ながら、その意図は十全に果たされているとはいいがたい。人々に建築原理について教え説くには、図版はともかく、そのテクストはあまりの混乱に満ちているのだ。それは、同時代のものたちに「この書物全体をほとんど知性のないものにさえしてしまうような、想像力の膨張と飛翔が見られる」★4と評されたほどであり、ルドゥーの《発見者》、ラメでさえ次のようにいうことを辞さない。
じじつ、現代においても自動書記に喩えられることのあるそのテクストは---彼の建築作品も古代の建築言語の意図的な誤用法によってシュール・レアリスム的であると評されることはあるが---論理的・体系的というには程遠く、建築の原理について論じていたかと思えば誰かまわず悪態をつき、文明論を綴っているその最中に激昂した調子で市民に呼び掛け啓蒙を促すといった、あまりに一貫性を欠いたものなのである。往時の王ルイ15世がルドゥーのことを「デリリアス」と評したといわれているが、それも肯ずけよう。そして、そうした混乱ぶりを目にすると、上述の意図はいわば大義にすぎず、本意は別のところにあったのではないかという疑念が生じたとしてもおかしくはない。すなわち、貶められた名誉の回復であり、建築に限らず不遇の作家がしばしば行う後生への期待がそれである。実施作のほとんどが破壊され、また投獄によりその存在さえ忘れ去られたひとりの建築家が、かつての業績を、たとえ図版という形でだけでも後に遺そう、そしてあわよくば、それによって歴史に名をとどめられたらと思うのは、持って然るべき願望といえるだろう。なにより、ルドゥー自身が次のように記してもいる。
私的な書簡などではなく『建築書』の趣意書という公刊物にこのような言葉を自ら綴るのだから、今からすれば確信犯的な匂いがしなくもないが、ともあれ、ここに見られる彼の切実な思いは、ラメを経てカウフマンに至り、まさに申し分のないかたちで果たされたといっていいだろう★7 。なにしろ、名誉の回復どころか、彼ら以降、ルドゥーは建築史において---いくぶん異端的な扱いながらも---《近代建築の祖》としての定位置を確保したのだから。『建築書』という書物が書かれていなければ、せいぜい歴史を周縁で彩る程度か、あるいはごく一部の者しか立ち寄ることのない場所に彼は置かれていたに違いない。
ところで、ここで次のように問うべきだろう。ルドゥーの意図はそうだとして(あるいは、どうであれ)、では、わたしたちはそこに何を読めばいいのか、と。もはやそれを---より正確にいえば《なにものをも》だが---規範として受け取ることができず、そしてまた、あらかじめ《歴史的》書物としてこの書を差し出されているわたしたちにとって、今、『建築書』を読むことの意義はどこにあるのだろうか・・・。ひとことでいえば、それは、そこに込められた《意志》を見ることにほかならない。建築への、あるいは建築からの意志。18世紀を建築にとっての《危機の時代》と称したのは磯崎新---この国において最も早い時期からルドゥーに着目し、そして誰よりも多く言及しつづけてきたのが彼である ---だったが、そのような時代にあってなお、いや、だからこそ建築へと/から向かおうとすること。「建築によって救済され得ぬものなど、この地上にはいないのだ」(L.103)---彼自身の言葉が示すように、ルドゥーにとっては、彼の生きる世界そのものが危機に瀕していたのであり、それを救えるのは至上の芸術である建築をおいてほかにない。そして、そのためにはまず、同じく危機の最中にある建築をその本来の在り方へと矯め直す必要があったのだ。だが、『建築書』を貫いているそのような意志はまた、あまりの強度と過剰さゆえに、建築に古代の輝きを取り戻すどころかむしろ、ある面においてはそこからの訣別を促さずにはおかないものでもあった(だが言い添えるなら、歴史を駆動する新しさとは常にそのようにしてあらわれてくるともいえるだろう)。
近代主義の行き詰まりが叫ばれて久しく、さらにはその先が見通せない中、もはやそんな意識さえ忘れ去られてしまったかのような現在において、18世紀というまさに近代が立ちあらわれつつあった歴史の大きな転換点に、建築の力に対する信念のもと、そのような意志を携えた建築家の思考の軌跡を改めて見ておくことは決して無駄にはならないだろう。