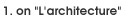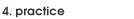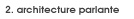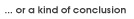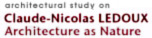18世紀の自然と芸術
18世紀は美学の世紀でもあった。理性の検証を受けた神や古典古代は、もはや美を支える絶対的な権威ではありえなかった。美を根拠づけるものを別のところに探さなければならない。美やそのあらわれである芸術作品は共約不可能なまでに多様ではあるが、しかし自然と同じようにその根底には普遍的な不壊の法則が存在するはずである。むろん、その法則はアカデミーによって外部から押しつけられた因習的な規則などではなく、美それ自体の本性から説明されるものでなければならない。多くの場合、それは自然の法則そのものであるとされた。「真なるもののほかに美しいものはない」のであれば、美は「常に真である自然」に拠るべきなのは当然であろう。すなわち、芸術は常に自然に即したものでなければならないのだ★9。
このように、18世紀は依然として自然を拠り所とするという意味で実在論的な芸術観から脱しきれてはいなかったが、しかし自然という概念が大きく変わった以上、前世紀のアカデミーが定立したような、現象としての自然の単なる模写だけでは、もはや芸術というに価しない。18世紀の芸術とは、所産的自然を忠実に模写 copie するのではなく、自然の法則に即することにより自然の創造行為そのものを模倣 imitation し、そうして自然の奥深い本質を顕在化するところの、いわばデミウルゴス的創造なのである。自然とは単なる被造物の総和ではなく、その最も深い意味において世界の形式と秩序を生み出す創造的力なのであり、これを模倣することによってのみ、美は真理と、そして芸術家は自然さらには神と競い合うことができるようになる。また、このようにして成し遂げられた芸術作品は、単に目に快いだけではなく、自然と同様、人びとの道徳を善き方向に導いていくものとして機能する(しなければならない)とも考えられた。ここでも『百科全書』に拠ろう。
ところで、18世紀は新古典主義の時代とも称されるが、上のような観点からは、古典古代の芸術はどのように捉えられたか。18世紀においては神同様に古典古代も相対化され、それはもはや不可疑の絶対的権威ではありえなかった。しかし、それでもなお、キリスト教やそれに基づく迷妄した人為に穢される前の無垢なる自然に最も近しく、それゆえその本質を最も良く模倣しえたものとして、ひとつの規範とみなされたことにかわりはなかった。
だが、その一方で、18世紀は次のような問いが盛んに論じられもした---古代とかれら《現代人たちmoderne》のどちらに優位をおくか、果たして後者が前者を凌駕することはできるのか、と。じつはこのような問いは、新旧論争として17世紀以来、人びとの常に話題とするところであったのだが、キリスト教の失墜により時間の観念が決定的な変質を蒙った18世紀は、それをよりリアルな、急迫した問題として受けとめていた★11。現代人の優位に関しては一貫してペシミスティックであったディドロ、自然の模倣をやめ想像力のみに芸術制作を委ねることで古代を超え出ることができるとするエドワード・ヤング、自然の観察に根差す造形芸術においては古代人に優位があるものの思想に基づく領域では現代人が勝るというシラー---数多くの論者がこの問いを論じたが、その立場はまさに十人十色であり、そのうえ論点も一定しない。そうした中、ルドゥーのとった立場はといえば、古代に基づきながらも現代人はそれを超え出ることができるとするものであった。ここで、ルドゥーの古代に対するスタンスを少し詳しく見ておこう。
規範として古代をしか認めないという点で、ルドゥーもまた多くの論者とかわりはない。彼にとって、古代に続く諸時代は一顧だに価しないものであった。
2000年前とはプラトンが生きた時代である。ルドゥーにとっては、その時代と彼が生きた時代は直結しているのだ。それらふたつの時代に挟まれた「無知の中間時代」(ダランベール)を彼は強く非難する。たとえばミケランジェロの作品も彼にとってはただの装飾過剰な粗悪品でしかない。
それだけではない。唯一の規範であるとはいえ、古代の傑作も、彼にしてみれば、建築が持つ力を完全に展開しているというには不十分なものであった。
古代に対する《現代》の関係を表す喩えとして、18世紀に頻繁に用いられた言葉に「巨人の肩の上にのった小人」というものがある。「巨人」とはいうまでもなく古代のことであり、かれら《現代人》は矮小な存在として文字どおりその巨人に肩を借りながらかろうじて高みを目指しているという、自嘲的なニュアンスがそこには読み取れる。この言葉は、ルドゥーの古典観もいいあらわしてもいるだろう。ただし、ネガティヴでもイロニーでもなく、考えうる限りの最もポジティヴな意味において。