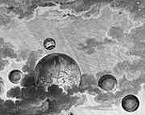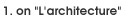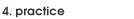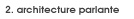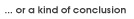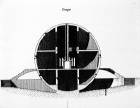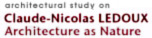ルドゥーの建築思想
ルドゥーにとって芸術とは「人類をその法則の支配下に置き(P.xi)」、人びとを強大な力で徳へと導いていくものであった。そして、その中にあって、建築こそが最高位を占めるものであり、それとともに、その製作者である建築家は芸術だけにとどまらず人間のあらゆる領域を統御し、世界そのものを改革することができる唯一者であるとも彼は考えていた。
その根拠を「世界のはじまり」といういわば始源性に求めているところが極めて18世紀的だといえようが、それはともかく、建築及び建築家に絶対的優位を認める《建築至上主義》ともいえる立場は、なにもルドゥー独自のものではなかった。表現の違いこそあれ、それは古代以来繰り返し述べられてきたことでもある。たとえば、「建築 architecture」の語源である architectonicé techné という言葉が示すように、古代ギリシアにおいて、建築術は「上位の術」であり、それゆえに建築家も単なる職人ではない「原理を知る工匠」であるとみなされていた★15。続くローマ時代には、ウィトルーウィウスが次のように記している。
そして、そのような建築・建築家観は、時を隔てた18世紀へと引き継がれる。
これは、『百科全書』編纂に当たり「建築」の項の執筆を任されもした啓蒙主義を代表する建築(理論)家 J=F・ブロンデルがその主著である『建築序説』に記した言葉である。彼は、ルドゥーの師でもあった人物であり、当然のことながらルドゥーは彼のこの著作を読んでいたのだろう★18。次のブロンデルの言葉は、『建築書』のテクストになんらの注釈もなく挿入されていれば、ルドゥー自身の言葉と見紛うほどである。
また、18世紀を通して広く読まれたマルク=アントワーヌ・ロージエの著書『建築試論』にも同様の記述を見ることができる。
これらの言葉からも、ルドゥーの、建築家を「世界の主権者(L.34)」とする態度は、単に彼の傲岸から発せられたものでなく、また、特に奇矯なものでもなかったことがわかるだろう。それはむしろ古典的・正統的とさえいえるものであり、その思想の少なくとも端緒において彼は建築史のいわば本流に位置する者たちと軌を一にしていたのである。ルドゥーを彼らから遠く隔たせているものがあるとすれば、それはそのような建築・建築家観を(語本来の意味で)ナイーヴに信じラディカルに押し進めたところにこそあるのだ。すなわち、建築家は《神》であり、その被造物である建築は《自然》と同一かまたはそれ以上のものになりうるという確固たる信念。
このあまりに彼らしい言葉は、建築とはその光明 eclair でもって人びとを照らし徳へと導いていく「啓蒙の芸術 l'art éclairé」であるということを当時のいわば最新の知的モードであった---18世紀は芸術をはじめとする人文諸分野と科学とは未分化の状態にあった---ニュートン的宇宙観のもとに謳い上げたものである。彼は多くの球体建築を描いているが、それらはこのような建築=天体説をまさにリテラルに具体化したものだといえよう。だが、ここで注目すべきは、その後半、建築家を造物主に匹敵するものとして捉えていることである。次の言葉はそれをより直截に語っている。
自己を神や創造主と同一視するこれらの言葉は、ともすれば単なる誇大妄想として扱われてきた。だが、その根底には先述のように、古典的な視座に基づいた、建築家が有する(べき)力の大きさ、扱う(べき)領域の広大さに対してのルドゥーの自負があるのだ。
ただ、ルドゥーの場合、その領域が人間のそれであるにとどまらず神の領域にまで広げられ、それとともに、その力もまた「普通の人間」ではない優れた才能というレベルから神や能産的自然のそれにまで高められたのである。このラディカルさ=徹底ぶりこそがルドゥーと他の建築家を分かつものだが、しかし、それさえも、より広く18世紀の芸術観・自然観に照らし合わせてみれば、彼の内で独自に育まれた妄想として片づけるわけにはいかない。ルドゥーは次のようにもいう。
なにの模倣をやめるのか。いうまでもなく自然である。芸術は自然の模倣でなければならないとする当時の芸術観がここでは明らかに意識されている。ルドゥーの先の言葉もそこから捉えられなければならない★21。
18世紀は依然として、芸術制作を自然の模倣に求める古代以来の実在論的世界観に基づいた芸術理論を固持してはいたが、それは単なる自然の模写 copie を意味するのではないということは先に述べたとおりである。ルドゥーの言葉をより深く理解するために、ここでは神という概念を中心に改めて当時の芸術観を見てみたい。
17世紀後半、ルイ14世治下のアカデミーでは、神学的秩序がまだ維持されていたこともあり、たとえばロジェ・ド・ピールやル・ヴランの絵画論にみられるように、自然の対象や効果をいかに再現するか、すなわち所産的自然をいかに「真実」として再現するかが自然の模倣理論の根幹をなすものであった★22。だが、18世紀になると自然の概念が大きく変容する。それはもはや神の被造物としての「理想型の一大貯蔵庫」ではなく、それ自らが「生成するエネルギー、倦むことなく産出する源泉」★23として捉えられるようになったのである。自然は単なる神の被造物などではなく、自らのうちに創造する力を持つ「生きた自然」なのだ。そして、人間もまた、被造物のひとつではなく、それ自身が神や自然に匹敵する創造的力を持つものとして考えられるようになる。このような自然や人間の概念の変化に伴い、自然の模倣をその根幹とする芸術理論も大きな変容を被ることになったのである。
これは、18世紀のフィロゾフたちによって再発見された17世紀の哲学者ライプニッツの言葉である。神と人間の主従関係が慎ましやかに保持されているとはいえ、17世紀にはすでにこのような思想が許されていた。そして、18世紀に至ると、その主従関係さえ廃絶される。当時の高名な思想家であったシャフツベリの芸術理論をカッシーラーは次のようにまとめている。
すなわち、18世紀における自然の模倣の本質とは、芸術家がその制作行為において神そのものとなることにほかならないのだ。したがって、ルドゥーの自己を神と称する先の言葉も、当時にあっては涜神的なものでも、特に奇異なものでもなかったはずである。むしろ、同時代の芸術理論に極めて敏感なものの発言としてそれを受けとめるべきだろう。彼は別のところで、芸術の制作行為を「人間がそれによって神となるところの創造(L.30)」とも述べており、この言葉などはそのままシャフツベリの美学理論の線上にあるものとして捉えることができる。
ところで、ここで念のためにいっておけば、「神になる」ことはいわゆるフリーハンドの自由を手に入れることを意味するのではもちろんない。あくまでも創造という行為を通じてこそ、そして自然の法則に従ってこそ、はじめて人間は神となりうるのである。ルドゥーもその点を指摘することを忘れてはいない。
ルドゥーにとっても自然の法則は絶対のものであり、建築家はそこから逸脱するならば「もはや求める核心へと到達することができない」ものだった。さらに彼は次のようにもいう。
つまり、彼が思い描く制作行為の在り様とは、まったき無からの創造ではなく、外部に質料因を求めるいわばデミウルゴス的創造なのである。こうした点からみても、ルドゥーは古代哲学に基づいた18世紀の芸術理論を正しく理解していたといえるだろう。ただ、繰り返せば、彼の独自性は、そのような芸術理論を文字どおりに受けとめナイーヴに押し進めたところにある。創造行為によって人間が神となりあるいはそれを超え出ることができるのなら、そうしてつくられた建築は自然と同じかまたはそれ以上のものになりうるという信念。確かに言葉だけをみれば、たとえ時代の思潮に拠っていたとはいえ、それは妄想とよばれるべきものかもしれない。だが、彼はまた、同じ信念のもと、数々の建築物を描き出してもいる。それらすべてを貫いているのは妄想などではなく、意志、建築を自然の高みにまで引き揚げ、そしてそのことを通して世界を変えようとする意志であり、それこそが彼の建築を独自なものたらしめているのだ。
《自然としての建築》---これはもちろん形態上の比喩を意味するのではない。18世紀の自然とは、まず第一に、人間のあらゆる領域を導いていくところの善かつ真である力、教訓としての機能そのものであった。ルドゥーの建築はなによりもその機能において自然と等しいものとして構想されているのである。建築によって人々を良き方向へと導いていくことができる。そして、その力は、彼の著作のタイトルが示すように、芸術はもとより道徳や政治にまで及ぶ。
建築によって社会/世界を改革しようとする確固たる意志。いみじくも美術史家ジャン・スタロバンスキーは、ルドゥーの建築の在り様を指して「意志の様式」とよんだが★27、《自然としての建築》とはすなわちそのような意志のラディカルなあらわれであり表明にほかならないのだ。