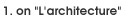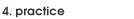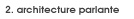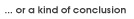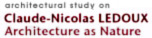18世紀の自然と芸術
人為あるいは人工の対概念、それが自然に関する今日の一般的理解であろう。そしてまた、そのような自然をわたしたちの外部に拡がる操作可能な客体として捉えることで技術や経済の目覚ましい進展を遂げてきたのが近代という時代である。
一方、ルドゥーの生きた時代はどうだったか。18世紀は、確かに近代へと繋がる自然観の萌芽は認められつつも、しかし、根底においてはやはり、それとは決定的に異なる自然観のもとにあった。自然とは、実体的なものでも、人間に対立するものでもない。それは、まず第一に、あらゆるものに刻印された永遠不変の真理であり、絶対普遍の原理であったのだ。ニュートンによって自然界のありとあらゆるものはひとつの厳密かつ単純な法則に従っていることが証明されたわけだが、その法則は真理の根拠と同一視されることにより、物理的世界はもとより人間の精神的・道徳的世界をもまたなんらかの形で支配していると考えられた。当時の知の体系である『百科全書』には次のような記述がある。
近代的な理性とは、自然に相対し、むしろそれを律するものとしてある。だが、18世紀はそうではなかった。当時の自然は、人間のうちに刻まれた真理、すなわち理性と同義のものだったのだ。そのことを最も熱烈に語っているのはやはりルソーである。
そしてまた、自然は18世紀において無限の多様性を有するものとしても捉えられた。大航海時代の幕開け、博物学の隆盛などにより(西欧にとって)未開の新世界やそれまで知られていなかった微細な差異が《発見》され、その結果、人間精神から生物にわたるまで同一のものは決してありえず、それこそが自然の特質だと考えられるようになったのである。《大博物学者》ビュフォンはいう、「自然のうちにはただ個の生物だけがあるにすぎず、種や属というものは一切存在しない」と。自然は、一切のカテゴライズを受け付けない。ありとあらゆるものが、自然というひとつの全体のなか、無限の差異、無限の多様性のもとに存在する。★4 フーコーは同一平面上に展開する秩序なき世界をエテロトピー=混在郷と称したが、18世紀の自然とはまさしくそのようなものとしてあったのだ。
このように、18世紀の自然は、一方では厳密かつ単純な法則として、そして他方では無限の多様性という相のもとに認識されていた。しかし、そのことが矛盾として捉えられることはなく、それどころかむしろ、自然の偉大さをそれは一層確信させるものだったのである★5。ここにこそ、18世紀の自然観の最大の特徴があるといってよい。
自然は自らのうちに単純な法則に従う造形原理としての力(能産的自然)を有し、その力の可能な限りの展開としてわたしたちの眼前に豊饒な無限の多様性(所産的自然)を繰り広げる。すなわち単純さと多様性は自然そのものに内在する力によって媒介されており、この力こそが世界を、そして人々をより善き方向に導いていく動因にほかならないと認識されたのである。
自然がこのように捉え直された以上、神もまた以前と同じではありえない。自然が自らを生み出し運動する力を有するのであれば、常に世界に目を配り、すべてがそこに帰されるような、いわば「世界の魂」(ニュートン)としての神は不要となる。理神論者にとっては神は「万物の主」か自然という「偉大な機械」の作者であるにとどまり★6、もはや「恩寵の国」から「人間の国」を圧迫することはない。そして、無神論者にとっては自然こそが神となり万物の起源となる★7。
18世紀はどちらかといえば理神論が多数を占めていたわけだが---ルドゥーもまたそうである---いずれの立場にせよ、自然はいついかなる場所でも善かつ真である、実体的というよりは機能的な意味を持つものであり、それはまた人間本性 nature として人びとのうちにも理性という名のもとに刻み込まれているものであった。政治、道徳、宗教・・・あらゆる人間の領域が自然によって導かれなければならない★8。しかし、キリスト教や理性に反する人為の諸規則・制度により、自然は見えなくなってしまっている。すべての領域において、それらが存在する以前、始源にはそうあった筈の無垢なる自然を復帰せしめよう。これこそが18世紀の人びとの最重要課題であったといえるだろう。