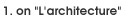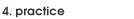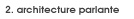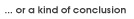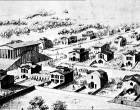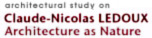自然としての建築
建築家はその創造する《力》において神と等しい。そうであるなら、それぞれの被造物である建築と自然もまた相等しいものとなるはずである★1。真の制作行為(=ポイエーシス)においては、原因の類比こそが重要であり、結果の類比はそこから自ずと生じてくる(にすぎない)ものであるのだから。
これまでみてきたように、ひとびとの本性に刻まれた理性としての自然、世界を善き方向に導く絶対普遍の真理としての自然こそが、自らの建築をそうあらしめようとルドゥーが望んだものだった。だが彼は、それだけではなく、あらわれにおいても建築は自然と相似ていなければならないと考えてもいた。もちろん、ルドゥーにとってそれは(所産的)自然が持つ有機的形態をそのまま自らの造形に取り込むといったレベルに留まるものでなかったことはいうまでもない。
18世紀において自然のあらわれは、これまでにもみてきたように、なによりもまず多様性として認識された。そして、ルドゥーにとって多様性とは「世界 le monde の魂」にほかならない。
世界は無限の差異に満たされている。そして、それを生み出しているのは自然の偉大な力にほかならない。そのような力の有り様においてこそ、建築は自然と類比関係を取り結ぶべきだとルドゥーは考えたのだ。すなわち、建築と自然との関係は、ひとつの建築物あるいはその部分が自然のある事物の様態を表すというような一対一対応にあるのではなく、ひとりの建築家の手による複数の建築物、その総体が自然の事物総体の体系---ここでは無限の多様性がそれである---を表出するという体系間の類比にこそ求められたのである。(構造主義の用語を借りるなら、対応のクラスが異なるのだ。)なぜなら、事物自体にではなく、それら事物間の無限の多様性にこそ、その制作者の力の強大さが表れるのだから。
ところで、ルドゥーは次のようにもいう。
では、この統一性は先に述べた多様性とどのようにして調停されるのか。「多様性の中の統一性」あるいは「統一性の中の多様性」は古典主義〜バロックを通じて理想とされた規範のひとつであったわけだが、ルドゥーにあってはそれはどのような形で具体化されたのか。
これも自然から説明される。自然はそのあらわれにおいて無限の多様性を示しはするが、その原因は単純な法則であり制作者であるところのひとりの神であった。つまり、自然の統一性は(理神論者にとっては)その造物主に帰せられたわけである。建築においても変わりはない。統一性はつくり手である建築家に帰せられるのだ。ルドゥーは上の言葉に続けていう。
そして、別のところで、建築家の心得を次のように記している。
古典主義建築における統一性とは、元来、「高貴なる単純さ」という理念へいたるためのひとつの規律であり、それはひとつの建築物における「部分」と「全体」との必然的な結びつきや、あるいは同じことだが形態上の均斉・均整を主に志向する概念であった★2。
だが、18世紀も後半になると、「ものごとには秩序が必要だとしても、変化もまた重要である。それがないと魂は退屈する」★3というモンテスキューの言葉がよく示すように、統一性が陥りがちな単調さに変化をもたらすものとして、今度は多様性が強調されるようになる。こうしてそれまで以上に「統一性の中の多様性」が称揚されることになったわけだが、しかし、ひとつの建築物のうちにそれら矛盾する2つの概念を具現化しようとするには自ずと限界があり、スタロバンスキーが指摘するとおり多くの場合かえってそれは「あまりに穏当」★4な結果にいたらざるを得ないものであった。いいかえるなら、古典主義というフレームの中、ひとつの建築物として破綻を来さないためには、多様性は統一性とのあいだで膠着状態に陥るほかなかったわけである。退屈からの逃走が新たな退屈を生むという逆説。
ルドゥーはしかし、そこからも逃れ去った。彼は、統一性を建築家の存在へ、多様性を彼がつくる(ひとつの建築物それ自体にではなく)複数の建築物間の差異へと、それらが適用・認識される場所をシフトすることにより、そうした因習的な規律から離脱をはかったのだ。そして、そのようにして軛を解かれ、いわばタブラ・ラサに置かれた建築物は、いかんなくその形態を自由に展開できることになったのである。
そのような多様性を最も顕著にあらわしているのがパリの市門群 Propylées de Paris (1784-1789) であろう。これはパリへの入市税を徴集するための文字どおり門としての機能を持つ建築物であり、群という名が示すように全部で54のものが実際に建てられた。だが、革命の際にほとんどが《市民》の手によって打ち壊されてしまい、今ではその全容は図版としてしかみる術はない★5。その図版をみると、それらはほとんど同一の機能を有するにもかかわらず、すべてが異なった形態を与えられているのだ。50以上もの多様性。だが、ひとつひとつを見較べてみればわかることだが、それぞれはまったく異なるわけではない。たとえばペディメントやコラムなどの構成要素に着目すると、それらは幾つかの建築物において同じであり限られた種類しかない。それら限られた構成要素を、ときには変形し、ときにはサイズを変えながら組み合わせることで豊かな多様性が生み出されているのである。いいかえるなら、ひとつの全体へと向けて部分が構想されるのではなく、部分=要素がまずあって、それらを自在に組み合わせることで、ひとつの、そしてさらには複数の(または高次の)全体がつくりだされているのだ。このような手法による限り、多様性はほとんど無限に延長可能となるだろう。
もはやそこでは古典主義〜バロックの全体性 wholeness は解体されてしまっている。無限の多様性を実現するには「充分に分節化され、より自由なシンタックスの可能性に開かれた徹底的な要素化」★6がなされなければならなかったのだ。そこにみられるのは、建築物を部品とその結合というシステムとしてとらえる「技術的思考」であり、多木浩二が「《物》の思考」とよぶものにほかならない★7。そして、そのような思考こそは、まさしく《近代》を特質づけるもののひとつであるといえるだろう。建築を自然へと向けて突き進めたあげく、逆説的にもルドゥーはそれまでの建築を解体し、そうしてそれを新たな地平=《近代》へと開くことになったのである。
ところで、多様性とは要素それ自体ではなく要素間の差異から生じるものである。一般に差異には、差異が確立されるための確固とした要素=項が存在することが含意されており、そのあいだにおいて差異が設定される。しかし、多様性のみを追求するならば、この差異のみが重要であり、要素=項は---ソシュールが言語についていうように★8---あまり問題とはならなくなる。無限の多様性を得ようとするつくり手の立場からすると、それはできるだけ簡素なほうがよいだろう。そして、建築形態において最も簡素なものとは純粋幾何学のそれにほかならない。---このように、建築形態の歴史的展開としてシンタクティックな観点からルドゥーの特徴のひとつであるプライマリーな幾何学形態の多用を説明付けることができるわけだが、ルドゥー自身は同じく言語を比喩として用いながらもいわばセマンティックな観点からその動機付けを行っている。そのあたりを次節でみてみたい。
(少し余談をすれば、全体性の解体とともに獲得された幾何学形態をいま一度ひとつの全体へと統合しようとした建築家としてル・コルビュジエの名を挙げることができるだろう。「建築とは、ヴォリュームの組み合わせが光のもとに織り成す正確で壮麗な知の協働である。」)